■子猫のワルツ #05 ![]()
衛藤が帰宅しようと音楽科棟のエントランスを出た時である。
「── おーい、そこのクソガキ」
上から声が降って来た。
ムカッ。
何度聞いてもムカつくこの声は──
振り返りつつ上を見上げると、音楽科棟と特別教室棟を繋ぐ2階の渡り廊下に、思った通りの人物がいた。
身体を乗り出すようにして手すりに凭れ、下を見下ろしている土浦梁太郎。
見下ろされていることがまたムカつく。
「………」
文句の一つも言ってやろうかとも思ったが、それすら腹立たしいので黙殺して踵を返す。
「おい、無視すんなって」
「……うるさいな── 人をクソガキ呼ばわりしといて、何の用だよ」
「あー悪い悪い、つい口から出ちまってな」
悪いと思っているようにはまるっきり見えない不敵な笑みを浮かべる梁太郎。
ありったけの力を目に込めて、下から睨めつける。
「……で?」
「あのさ、お前、何かスポーツできるのか?」
「……はあ?」
何を言ってくるかと思えば、『スポーツできるか』だと?
予測していなかった内容に衛藤はすっかり毒気を抜かれ、睨みつけるのも忘れて目をぱちくり。
「いや、ずっと一緒に昼バスケやってた先輩が卒業してから、恒常的にメンツが足りなくてな── どうだ?」
「どうだ、って言われても……バスケはマズいだろ、楽器やってる人間としては」
「そこまで本気じゃやらないさ。なんならサッカーでもいいぜ?」
身体を動かすのは嫌いではない。
むしろ好きである。
だがこの男と一緒に、というのが甚だ不本意なのだ。
ならばすっぱり拒絶してしまえばいい。
しかしそれができないのは、『彼女』の存在。
彼女の側には大抵この男がいる。
裏を返せば、この男の側に彼女がいる確率が非常に高いのである── 悔しいことに。
ひょっこり突きつけられた大きな選択に衛藤が逡巡していると、
「ごめーん、お待たせっ!」
特別教室棟からぴょんと飛び出してきたのは、彼を悩ませる最大の原因である『彼女』── 日野香穂子だった。
香穂子は「何してるの?」と梁太郎の隣に並ぶと、下を覗き込む。
そこにいた衛藤に気づくと、全開のスマイルでひらひらと手を振って、
「あ、桐也くんだ。やっほ〜♪」
その瞬間、当然ながら衛藤の頬はだらしなく緩んだ。
「ふたりで何話してたの?」
「ああ、あいつを昼バスケに誘ってたんだ」
「あー、火原先輩の代わりかぁ」
「まあな」
顔を見合わせて楽しげに会話を交わすふたりを見ていたくなくて、衛藤が再び踵を返そうとしたその時。
「── そういえば最近、フットサルに誘ってくれないよね?」
ぴたりと足が止まる。
彼女が参加するのなら、自分も参加しないわけにはいかないではないか。
「ていうか、最初の1回だけだったよね、誘ってくれたの」
「あ……そ、それはだな……」
詰め寄る香穂子。
対して梁太郎は少し赤らめた顔をあさってのほうへと逸らしている。
「メンバー足りないなら、私を誘ってよ〜」
「う……」
言葉に詰まった梁太郎は困ったようにガリガリと頭を掻くと、彼女の耳元に顔を寄せて何かを囁いた。
「へ? ……『ピンク』?」
「だから……解れよ。あの普通科の短いスカートで、足を高く蹴り上げたらどうなると思ってるんだ?」
ぽんっ。
香穂子の顔が爆発したかのように真っ赤に染まった。
「あぅ……そ、それって……」
「ああ、他のヤツら、急に『用事を思い出した』って抜けてっただろ……気になってゲームしてられねぇって」
ぷしゅぅ、と空気が抜けたように、手すりに置いた腕に顔を埋める香穂子。
「……………見た?」
「は…?」
「梁も、見た?」
「………み、見てない」
「ほんとに?」
「う……」
今度は梁太郎の顔までが火がついたように赤くなった。
がばっと身体を起こした香穂子は、
「もうっ! なんでその時に教えてくれなかったのよっ!」
「あ、あの頃はそういう話できるような関係じゃなかっただろうがっ!」
「でもそれとなく教えてくれたっていいじゃないっ!」
「んな無茶苦茶言うなっ! うわっ!」
振り上げられた彼女の拳から逃げるように、梁太郎は音楽科棟へと駆け込んだ。
「ちょっ、待ちなさいっ!」
彼を追って、彼女もまた音楽科棟へと飛び込んでいく。
ぷっつりと断ち切ったように辺りがしんと静まり返った。
入れ替わるようにして、あちこちから聞こえる楽器の音が耳に届く。
「……アホらし」
はふ、と大きな溜息を吐いて、衛藤は今度こそ正門へと向かって歩き始めた。
二人に釣られたのか、彼もまたほんのりと顔を赤く染めていることに、彼自身気づかぬままに──
〜おしまい〜
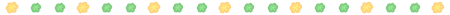
【プチあとがき】
ビバ、バカップル!
衛藤くんは『横恋慕』というよりも『とばっちり』になりつつあるなぁ…
いや、それでいい(笑)
フットサルは昼休み会話より。
ちょっとしたニヤリポイントに気づきましたか?
【2009/04/19 up】